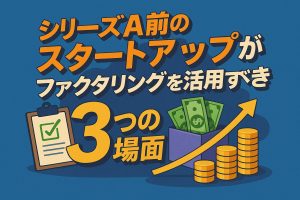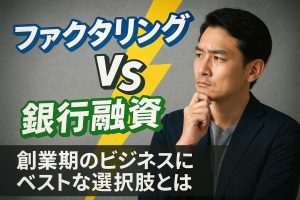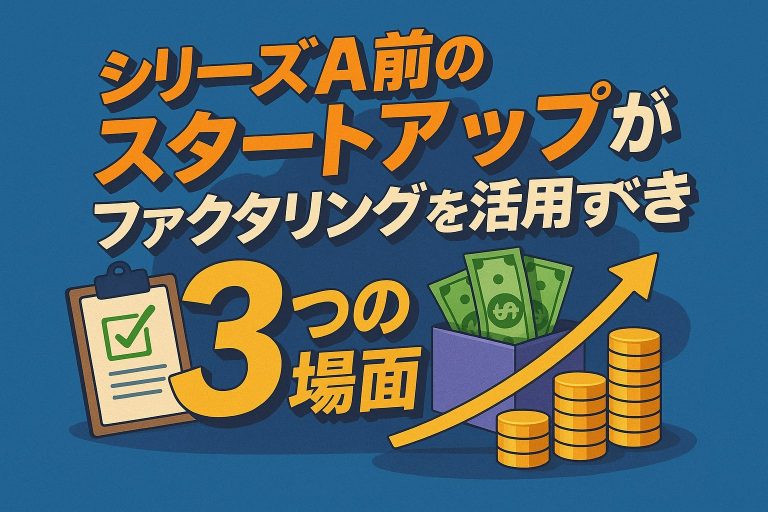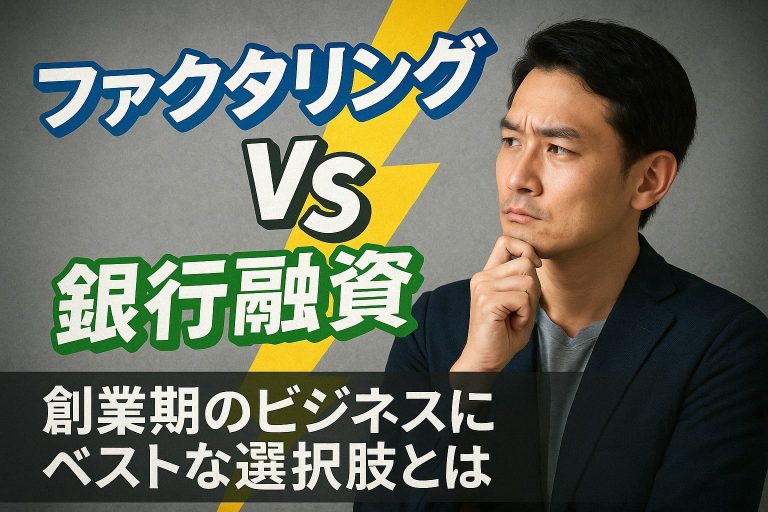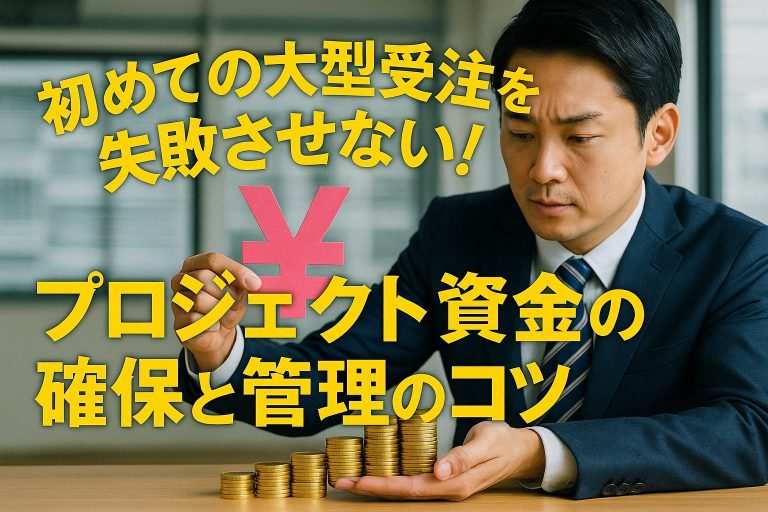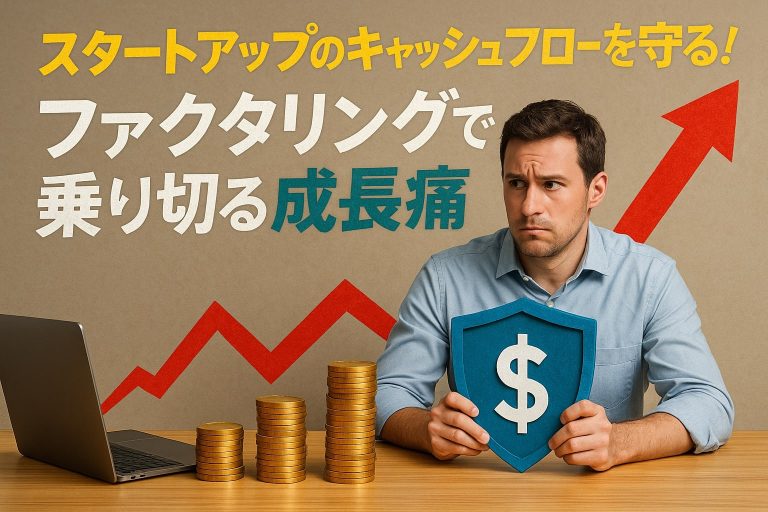「資金が底をつく」――これは多くの起業家にとって悪夢のような言葉です。
私は10年近く銀行の法人営業として中小企業の資金繰りに携わり、その後はコンサルタントとして数多くのスタートアップの財務に向き合ってきました。
そこで目の当たりにしたのは、優れたビジネスプランを持ちながらも短期的な資金ショートで潰れていく起業家たちの姿でした。
多くの方が「日本政策金融公庫の創業融資」を頼りにしますが、実は審査や入金までの期間が思った以上に長く、その「待ち時間」で事業が立ち行かなくなるケースが少なくありません。
本記事では、そんな創業期の資金調達において見落とされがちな選択肢「ファクタリング」に焦点を当てます。
特に「創業融資」と「ファクタリング」を併用することで、資金繰りの幅を広げる方法をお伝えします。
銀行、コンサル、ライターとして現場に立ち会ってきた視点から、リアルな資金調達の知恵をお届けします。
目次
創業初期の資金繰りのリアル
「創業融資」だけでは足りない現実
私が銀行員時代に見てきた創業初期の企業は、ほぼ例外なく「想定外の出費」との戦いでした。
事業計画で緻密に計算していても、実際に事業をスタートさせると予測できない支出が次々と発生します。
公庫や銀行の創業融資は確かに低金利で有利ですが、融資実行までに最短でも1〜2ヶ月、場合によっては3ヶ月以上かかることも珍しくありません。
その間の運転資金をどう捻出するかが、多くの起業家にとって大きな課題となっています。
さらに、創業融資の金額は一般的に希望額を下回ることが多く、「満額出た!」というケースはむしろ稀です。
結果として、創業融資だけを資金調達の柱にしている起業家の多くが、スタートダッシュの段階で躓いているのが現実なのです。
起業家が直面する資金ショートの典型パターン
私が現場で観察してきた資金ショートには、いくつかの典型的なパターンがあります。
1. 初期投資の見積もり誤り
- 店舗改装や機器調達が予算オーバー
- 許認可取得に想定外の時間とコストがかかる
- 採用コストが膨らむ
2. 売上計画の遅延
- 営業開始が遅れる
- 顧客獲得に時間がかかる
- 最初の請求サイクルが想定より長い
3. 入金サイクルの壁
- B2B取引の場合、契約から入金まで3〜4ヶ月かかることも
- 大企業との取引では翌月末や翌々月末支払いが一般的
- 初回取引では前払いが難しいケースが多い
これらの問題は、創業計画の段階ではなかなか気づきにくい落とし穴です。
銀行での融資審査においても、このような「タイミングのズレ」に対する備えが不十分なケースを数多く見てきました。
よくある失敗談:審査待ち・入金待ちで詰む
「今月末までに仕入れ代金を支払わないと、初回納品に間に合わない。でも公庫からの融資はまだ審査中で、どうしようもない…」
これは私がコンサルタントとして相談を受けた、ある食品製造業の起業家の言葉です。
彼は事業計画書を丁寧に作り、創業融資の申請も早めに行いました。
しかし、審査の過程で追加資料の提出を求められ、予想以上に時間がかかってしまったのです。
このような状況は決して珍しくありません。
創業融資の審査期間は、申請の混雑状況や審査担当者の判断によって大きく左右されます。
特に創業融資は既存企業への融資よりも慎重な審査が行われるため、想定以上に時間がかかることが多いのです。
また、融資が承認された後も実際の入金までには時間がかかります。
書類の作成や押印、担保設定などの手続きを経て、ようやく入金となるのです。
「承認されたから大丈夫」と安心していると、実際にお金が使えるようになるまでの「ラストワンマイル」で詰んでしまうケースも少なくありません。
典型的な失敗シナリオ
- 創業融資の審査に自信があり、その前提で事業をスタート
- 審査が長引き、その間の資金繰りが悪化
- 個人のクレジットカードや親族からの借入で凌ごうとする
- 融資承認まで何とか持ちこたえたが、入金までの橋渡し資金が尽きる
- ビジネスチャンスを逃す、または事業継続が困難になる
こうした状況を回避するには、創業融資と並行して「即時性のある資金調達手段」を確保しておくことが非常に重要なのです。
ファクタリングとは何か?その仕組みと基本
ファクタリングの基本構造と2つのタイプ(2社間/3社間)
ファクタリングとは、シンプルに言えば「売掛金の買取」です。
企業が保有する売掛金(まだ支払いを受けていない請求書)を、専門業者が割り引いて買い取り、即座に現金化する仕組みです。
融資ではなく「売買」の形を取るため、審査基準が緩く、スピーディーに資金調達できることが最大の特徴です。
ファクタリングには大きく分けて2つのタイプがあります。
2社間ファクタリング
- 売掛先に知られずに利用可能
- 売掛先への通知や承諾が不要
- 一般的に手数料(割引率)が高め
- スピード重視の場合に選ばれることが多い
3社間ファクタリング
- 売掛先を含めた3社での契約
- 売掛先の承諾が必要
- 一般的に手数料が低め
- 継続的な利用に向いている
起業初期では、取引先との関係を考慮して2社間ファクタリングを選ぶケースが多いようです。
また、最近では「請求書ファクタリング」と呼ばれる、発行したばかりの請求書を即座に現金化するサービスも登場しています。
銀行融資との違い:信用ではなく「売上」に着目
銀行融資とファクタリングの最大の違いは、判断基準が「企業の信用力」ではなく「売掛金(売上)の確実性」にある点です。
| 特徴 | 銀行融資 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 審査基準 | 事業の継続性、返済能力 | 売掛金の確実性 |
| 創業期の難易度 | 高い(実績が必要) | 比較的低い(売上があれば可能) |
| 資金調達までの期間 | 1〜3ヶ月 | 最短即日〜1週間 |
| コスト | 年利1〜5%程度 | 月利1〜10%程度(年利換算で高い) |
| 返済義務 | あり | なし(売買のため) |
銀行融資は長期的な事業計画と返済能力を重視するのに対し、ファクタリングは「既に発生している売上」の確実性だけを見ます。
そのため、創業間もない企業でも、確実な売掛先があれば利用可能なのです。
特に「大企業や官公庁との取引」がある場合は、ファクタリング会社の評価も高くなり、条件も有利になる傾向があります。
起業初期での利用メリットと注意点
起業初期にファクタリングを活用する主なメリットは以下の通りです。
- スピード: 最短で即日から数日で資金化が可能
- 審査の柔軟性: 創業間もなくても利用できる
- 負債にならない: 貸借対照表上の借入金として計上されない
- 無担保・無保証: 個人保証や担保が不要なケースが多い
- 売上が確定していれば利用可能: 創業期特有の「実績不足」の壁を超えられる
一方で、以下のような注意点もあります。
「ファクタリングは緊急時の救急車。使い方を間違えると、かえって体力を奪います」
これは私がセミナーでよく使う表現です。
具体的な注意点としては:
- コストが高い: 年利換算すると20〜30%以上になることも
- 短期的な解決策: 長期資金には不向き
- 依存するとキャッシュフローが悪化: 常態化すると実質的な収益を圧迫
- 業者選びが重要: 悪質な業者も存在する(後述)
ファクタリングは「ブリッジファイナンス(つなぎ融資)」としての活用が最適です。
創業融資が実行されるまでの短期間や、大型案件の入金待ち期間を乗り切るための「時間稼ぎ」として考えるべきでしょう。
ファクタリングが特に有効なケース
- 創業融資の審査中で、緊急の資金需要がある
- 大口顧客からの入金が数か月先だが、仕入れや人件費の支払いに迫られている
- 短期間に集中的な資金が必要な繁忙期や新規プロジェクト立ち上げ
- 創業融資では賄えない突発的な支出が発生した
創業融資とファクタリングは両立できるのか?
両立のカギ:資金使途とタイミングの設計
「創業融資を受けようとしているのに、ファクタリングも利用して大丈夫なの?」
これは創業者からよく受ける質問です。
結論から言えば、適切に設計すれば両立は可能です。
むしろ、うまく組み合わせることで資金調達の幅が広がります。
両立のポイントは「資金使途の棲み分け」と「タイミングの設計」にあります。
資金使途の棲み分け例:
- 創業融資→長期的な設備投資、初期の固定費
- ファクタリング→短期的な運転資金、突発的な支出
タイミングの設計例:
- 創業融資の申請を行う
- 審査中に発生する資金需要をファクタリングでカバー
- 融資実行後、余裕が出てきたらファクタリングの利用を減らす
この「ブリッジファイナンス」としての活用方法が、最も効果的かつ健全な併用法です。
事例:IT開発企業Aの場合
あるITベンチャーの創業者は、官公庁からの大型開発案件を受注しました。
案件自体は魅力的でしたが、入金までに6ヶ月以上かかる条件でした。
創業融資は審査中で、人材確保のための資金が急務だったため、官公庁向け案件の請求書をファクタリングで現金化。
その後、創業融資が実行され、次の案件からは融資資金で運転資金をまかなえるようになりました。
このケースでは、ファクタリングがなければ大型案件を受注できず、成長の機会を逃していたでしょう。
融資担当者の視点:併用でマイナス評価されるケース
一方で、融資担当者の視点からすると、ファクタリングの利用がマイナス評価につながるケースもあります。
私が銀行員として融資審査に携わっていた経験からすると、以下のようなパターンは注意が必要です。
- 過度に依存しているケース
融資申請時の資金繰り表で、継続的なファクタリング利用が前提になっている場合は「根本的な収益構造に問題あり」と判断されることがあります。 - 隠れて利用しているケース
融資審査の過程で「実はファクタリングも使っています」と後から伝えるのは、信頼関係を損なうリスクがあります。 - 資金使途が重複するケース
創業融資と同じ目的(例:設備投資)のためにファクタリングも利用している場合、計画性を疑問視されることもあります。
「上手に併用した事例」から学ぶ実践知
ここでは、実際に創業融資とファクタリングを上手に併用した事例から、実践的なポイントをご紹介します。
飲食店Bの事例:開業準備と運営のギャップを埋める
新規飲食店の開業を計画していたB氏。
公庫の創業融資で店舗改装費と初期在庫を賄う計画でした。
融資は承認されたものの、実際の入金までに時間がかかり、すでに予約していた職人の着手金支払いに間に合わなくなりました。
そこで、前職の会社から請け負っていたコンサルティング業務の請求書をファクタリングで現金化。
工事を予定通り進め、開業後に入金された融資金で運転資金を確保しました。
ITサービス会社Cの事例:大型受注と人材確保のジレンマ解決
SaaS企業の創業者C氏は、大手企業からシステム開発を受注。
この案件を進めるには追加エンジニアの採用が必須でしたが、入金は納品後の90日後。
創業融資は設備投資と最低限の運転資金に充てる計画だったため、人件費に不足が生じました。
そこで受注契約書をもとにファクタリングを利用し、人材確保のための資金を調達。
納品後、顧客からの入金で運転資金を回復させました。
両立成功のための3つの原則
これらの事例から見えてくる成功の原則は以下の3点です。
- 創業融資担当者への事前相談
「ファクタリングの利用も検討している」と伝え、理解を得ておくことで、後のトラブルを避けられます。 - 明確な出口戦略
「いつまでに」「どうやって」ファクタリングから脱却するかの具体的な計画を持つことが重要です。 - 資金繰り表での可視化
創業融資とファクタリングの両方を組み込んだ詳細な資金繰り表を作成し、キャッシュフローを正確に把握することが不可欠です。
これらのポイントを押さえることで、「創業融資だけでは足りない部分」を賢くカバーしつつ、資金繰りの安定化が図れるでしょう。
ファクタリング活用の実践ステップ
ステップ1:資金繰り表を用いた必要額の算出
ファクタリングを活用する前に、まずは正確な資金繰り表を作成し、「いつ」「いくら」の資金が必要かを明確にすることが重要です。
資金繰り表作成のポイントは以下の通りです。
1. 週単位での細かい予測
- 月単位だけでなく、週単位で入出金を予測する
- 特に創業期は想定外の支出が多いため、余裕を持たせる
- 銀行の入金サイクル(平日のみ)も考慮する
2. 最悪シナリオの想定
- 売上の遅延や減少を想定した複数のパターンを作成
- 特に最初の3ヶ月は売上を50%減で計算するなど厳しめに見積もる
- 緊急支出枠を設けておく(月間予算の10%程度)
3. ファクタリング利用期間の明確化
- いつからいつまでファクタリングを利用するか
- どの売掛金を現金化するか
- 手数料コストの試算と収益への影響
資金繰り表のサンプル図
以下のようなシンプルな資金繰り表を作成しましょう。
| 週 | 前週繰越 | 入金予定 | 出金予定 | 差引残高 | 対策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1週 | 100万円 | 0円 | 50万円 | 50万円 | – |
| 4/2週 | 50万円 | 0円 | 80万円 | ▲30万円 | ファクタリング検討 |
| 4/3週 | ▲30万円 | 200万円 | 100万円 | 70万円 | – |
| 4/4週 | 70万円 | 0円 | 120万円 | ▲50万円 | 創業融資入金予定 |
このように資金がショートする週を特定し、その金額と期間から最適なファクタリング利用計画を立てます。
ステップ2:ファクタリング業者の選定と比較ポイント
ファクタリング業者選びは非常に重要です。
悪質な業者も存在するため、以下のポイントを参考に慎重に選定してください。
業者選定の5つのチェックポイント
❶手数料率の透明性
- 手数料率が明確に表示されているか
- 隠れたコストがないか(事務手数料、調査費など)
- 年率換算するといくらになるか
❷契約書の明瞭さ
- 契約内容がわかりやすく記載されているか
- 専門用語が多用されていないか
- 解約条件や特約事項が明確か
❸実績と信頼性
- 運営会社の情報が公開されているか
- 金融庁や協会などへの登録状況
- 口コミや評判(特に否定的な情報)
❹対応の丁寧さ
- 質問に対して明確に回答してくれるか
- 強引な営業をしていないか
- 電話やメールの対応が迅速か
❺資金調達実績
- 特に自分の業界での利用実績があるか
- スタートアップ支援の実績があるか
- 大手企業との取引実績があるか
創業者に人気の比較的安全なファクタリング業者例
- 大手金融グループ系のファクタリング会社
- スタートアップ特化型のファクタリングサービス
- 業界特化型のファクタリングプラットフォーム
これらの会社は比較的透明性が高く、創業期の企業にも対応していることが多いです。
ただし、具体的な業者名は変動するため、最新の情報を調査することをお勧めします。
創業期の企業にとっては審査の通りやすさも重要な選定ポイントです。
資金調達を急いでいる場合は、「審査が甘いファクタリング10選【審査通過率85%以上】」などの比較情報も参考にすると良いでしょう。
特に創業間もない企業や過去の取引実績が少ない場合は、審査基準の緩やかな業者を選ぶことで、資金化までの確実性が高まります。
ステップ3:契約・入金までの具体的な流れ
ファクタリングの契約から入金までの一般的な流れは以下の通りです。
契約から入金までの流れ
❶問い合わせ・申し込み
- オンラインフォームか電話で問い合わせ
- 基本情報と売掛金の情報を提供
❷必要書類の準備と提出
- 売掛先との契約書
- 請求書のコピー
- 納品書や検収書のコピー
- 会社の登記簿謄本(個人事業主の場合は開業届)
- 本人確認書類
❸審査と買取価格の提示
- 売掛先の信用力を確認
- 買取価格(割引率)の提示
- 条件交渉(可能な場合)
❹契約締結
- 契約書の確認と署名
- 売掛債権譲渡の手続き(3社間の場合は売掛先の承諾も)
❺入金
- 契約完了後、最短即日〜数日で指定口座に入金
- 入金額は請求額から手数料を差し引いた金額
契約時の注意点
- 契約書は必ず全文読む
条項の中に不利な内容が含まれていないか確認する - 手数料の計算方法を確認
パーセンテージだけでなく、計算の基準になる金額もチェック - 追加費用の有無を確認
事務手数料や振込手数料など、手数料以外のコストの有無 - 遅延時のペナルティを確認
売掛先からの入金が遅れた場合の対応やペナルティ - 契約書のコピーを必ず保管
後のトラブル防止のため、契約内容を記録として残す
ステップ4:創業融資とどう併せるかの戦略立案
創業融資とファクタリングを効果的に併用するための戦略立案方法をご紹介します。
併用パターン別の戦略例
パターン1: ブリッジファイナンス型
- 創業融資の入金待ち期間をファクタリングで乗り切る
- 融資入金後はファクタリングを終了
パターン2: 繁閑対応型
- 創業融資は固定費と閑散期の運転資金に充てる
- 繁忙期の一時的な資金需要はファクタリングで対応
パターン3: 大型案件対応型
- 創業融資は通常の運転資金に充てる
- 大型案件の仕入れ資金などはファクタリングで対応
タイミング戦略の具体例
特に「創業融資入金前のつなぎ資金」としてファクタリングを活用する場合のタイムラインです。
- 創業融資の申請(0日目)
- 資金繰り表で資金ショートするタイミングを特定(〜7日目)
- ファクタリング会社への相談と準備(〜14日目)
- 資金ショート前にファクタリング契約(〜21日目)
- 創業融資審査の追加資料提出など(〜30日目)
- 創業融資承認(〜45日目)
- 創業融資入金(〜60日目)
- ファクタリングの清算または縮小(60日目〜)
金融機関への説明戦略
創業融資の審査中にファクタリングの利用を検討する場合、融資担当者への説明方法も重要です。
- 隠さずに伝える
「つなぎ資金として一時的に利用する予定」と率直に伝える - 資金計画の堅実さをアピール
「万が一の備え」として計画していることを強調 - 出口戦略を明確に
「融資入金後はファクタリングから脱却する」計画を示す - 総合的な資金調達の一環と位置づける
「多様な資金調達手段を組み合わせる経営の柔軟性」としてポジティブに説明
実例を示しながら、「ファクタリングを利用する=融資が必要ない」わけではなく、むしろ「融資を最大限に活用するためのつなぎ」という位置づけであることを伝えましょう。
起業家が陥りがちな誤解とトラブル回避術
「ファクタリング=怪しい」は本当か?
「ファクタリングは怪しい」という印象を持つ方は少なくありません。
確かに一部の悪質な業者の存在や、高額な手数料から否定的なイメージが形成されています。
しかし、適切に利用すれば有効な資金調達手段となり得ます。
誤解の正体を解明する
ファクタリングに関する主な誤解とその真相を整理しました。
- 誤解:「ファクタリングは違法な高金利貸付」
真相:適切に実施されるファクタリングは「金銭の貸付」ではなく「債権の売買」であり、法的に問題ありません。 - 誤解:「審査が簡単なのは何か裏がある」
真相:銀行融資と異なり、審査は「売掛先の支払能力」を重視しており、創業者自身の信用力には依存しない別の審査ロジックを使用しているだけです。 - 誤解:「創業融資より不利な選択肢でしかない」
真相:スピードと柔軟性では創業融資より優れており、短期的な資金需要には適していることもあります。 - 誤解:「ファクタリングを使うと信用を失う」
真相:資金調達の多様化として適切に説明すれば、むしろ資金繰りへの意識の高さをアピールできることも。
健全なファクタリング業者の見分け方
信頼できるファクタリング会社の特徴は以下の通りです。
- 会社情報や代表者の情報が明確に公開されている
- 手数料や条件が透明で、契約前に詳細な説明がある
- 強引な営業や即決を迫る態度がない
- 顧客の事業内容や資金ニーズを丁寧にヒアリングする
- 業界団体への加盟や金融機関との提携実績がある
手数料・契約条件で泣かないために
ファクタリングを利用する際に最も注意すべきは、手数料と契約条件です。
知識がないまま契約すると、想定外のコスト負担に悩まされることになります。
手数料を正しく理解するための3つのポイント
❶割引率だけでなく年率換算で考える
「手数料10%」と聞いて「金利10%と同じか」と思うのは大きな誤解です。
例えば請求書の支払いサイトが2ヶ月の場合、10%の割引で現金化すると年率換算では60%相当になることも。
常に年率換算で考えることで、実質的なコストを把握できます。
❷総額ではなく実質手数料を計算する
例えば100万円の請求書を90万円で買い取ると提示された場合:
- 表面上の手数料:10万円(10%)
- 実質手数料率:10万円 ÷ 90万円 = 約11.1%
実際に手元に入る金額を基準に手数料率を計算すべきです。
❸追加コストの確認
契約書に記載される可能性のある追加コストには以下のようなものがあります:
- 事務手数料
- 振込手数料
- 調査費用
- 遅延ペナルティ
- 契約解除料
これらが発生する条件と金額を必ず確認しましょう。
契約時の危険信号
以下のような状況は注意が必要です:
- 極端に高い手数料
業界平均(例:2ヶ月サイトで5〜15%程度)を大きく超える割引率 - 書面での契約書がない
口頭での約束や簡易な覚書のみの契約 - 説明を急かされる
十分な説明時間がなく、質問に対して明確な回答がない - 不明瞭な条項
専門用語が多用されており、意味を確認しても曖昧な回答しか得られない - 未払い時の責任が不明確
売掛先が支払わなかった場合の対応が契約書に明記されていない
相談先としての税理士・資金調達アドバイザーの役割
ファクタリングの活用を検討する際は、専門家への相談も有効です。
特に税理士や資金調達アドバイザーは、第三者視点でのアドバイスを提供してくれます。
税理士に相談するメリット
- 会計上の処理方法のアドバイス
ファクタリングの会計処理は通常の融資と異なります。
売掛金の消込方法や手数料の計上方法など、適切な会計処理について助言が得られます。 - 税務上の影響の確認
手数料は経費計上できますが、その方法や時期についてアドバイスが必要です。 - 資金繰り全体の最適化提案
ファクタリングと他の資金調達手段を比較し、総合的な視点からのアドバイスが期待できます。
資金調達アドバイザーの活用法
- 複数業者の比較サポート
業界に精通したアドバイザーは、適切なファクタリング業者を紹介してくれることがあります。 - 交渉力の強化
専門家が入ることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。 - 出口戦略の立案支援
ファクタリングから他の資金調達手段へのスムーズな移行方法のアドバイスが得られます。 - 金融機関との交渉サポート
創業融資とファクタリングを併用する際の金融機関への説明方法についてサポートしてくれます。
Q&A:ファクタリング利用に関するよくある質問
Q1: 創業間もない状態でもファクタリングは利用できますか?
A1: はい、利用可能です。
ファクタリングは企業の信用力ではなく、売掛先(請求書の支払元)の信用力を重視するため、創業間もない企業でも売掛先が信頼できる企業であれば利用できます。
特に、公的機関や上場企業との取引がある場合は条件が有利になりやすいです。
Q2: ファクタリングの利用は財務諸表にどう影響しますか?
A2: ファクタリングを利用すると、売掛金が減少し、現金が増加します。
通常の借入と異なり負債として計上されないため、財務健全性の指標である「自己資本比率」には影響しません。
ただし、ファクタリング手数料は「支払手数料」などの費用として計上されるため、利益が減少する点には注意が必要です。
Q3: 銀行融資の審査中にファクタリングを利用すると、審査に悪影響がありますか?
A3: 適切に説明できれば、必ずしも悪影響はありません。
融資担当者に対して「融資実行までのつなぎ資金として一時的に利用する」と明確に説明し、出口戦略も示すことが重要です。
ただし、融資申請時には利用予定である旨を伝えておくことをお勧めします。
後から「実はファクタリングも使っています」と伝えると、信頼関係に影響することがあります。
Q4: 個人事業主でもファクタリングは利用できますか?
A4: はい、個人事業主でも利用可能です。
法人よりも書類が簡素化されることもありますが、売掛先の信用力は同様に重視されます。
必要書類としては、開業届、確定申告書、身分証明書、売掛金の証憑(請求書・契約書など)が一般的です。
Q5: ファクタリングと単純な「請求書の前払い」はどう違うのですか?
A5: 本質的な違いは「誰がリスクを負うか」です。
請求書の前払いは、あくまで顧客(支払元)があなたに前払いするだけで、支払い義務は変わりません。
一方、ファクタリングは売掛債権自体を売却するため、原則として売掛先が支払わなかった場合のリスクはファクタリング会社が負います(ただし契約条件によって例外もあります)。
まとめ
創業期の資金調達は、単一の手法に頼るより、複数の選択肢を持つことが重要です。
私がこれまで見てきた多くの起業家の成功事例は、「創業融資」という大きな幹を持ちつつも、「ファクタリング」という柔軟な枝を賢く活用していました。
ファクタリングは決して「怪しい」資金調達手段ではなく、適切に使えば創業期の命綱となる可能性を秘めています。
特に創業融資の審査中や入金待ち期間の「ブリッジファイナンス」として活用する価値は大きいでしょう。
重要なのは以下の3点です。
- 正確な資金繰り計画を立てる
いつ、いくらの資金が必要か、そしていつ返済・清算できるかを明確にする - 信頼できる業者を選ぶ
手数料の透明性、契約内容の明確さを重視する - 出口戦略を持つ
ファクタリングはあくまで「一時的な」資金調達手段として位置づける
私自身、銀行員時代に「もう少し待てば融資が通ったのに」と悔しい思いをした経営者を何人も見てきました。
しかし、資金繰りに「待った」はありません。
創業期の資金調達は、時に「速さ」が「安さ」に勝ることを覚えておいてください。
「ファクタリングを知っているか知らないか」が命運を分ける——これは誇張ではなく、私が現場で実際に見てきた現実です。
この記事が、これから起業する方、あるいは創業期の資金繰りに悩む方の一助となれば幸いです。