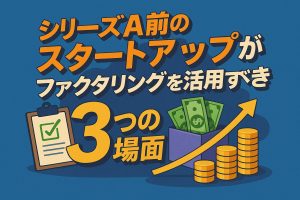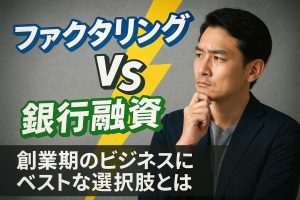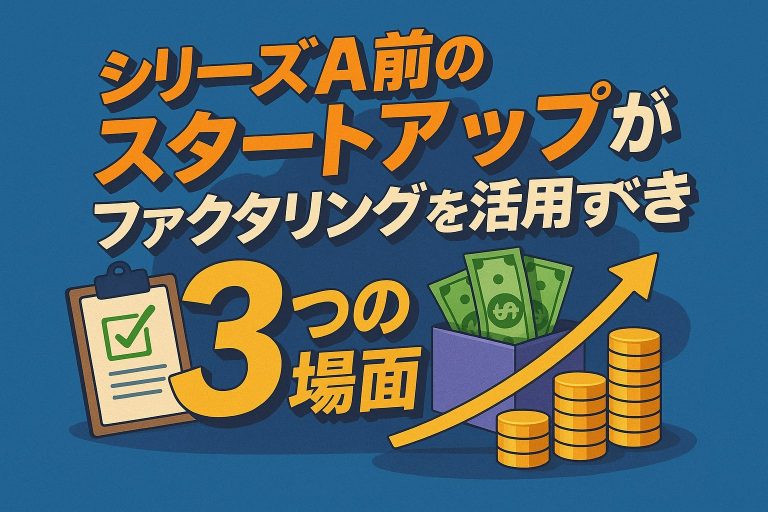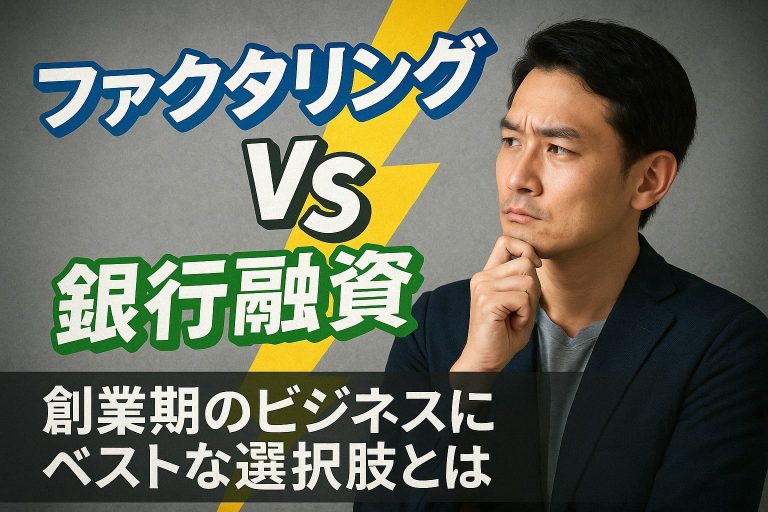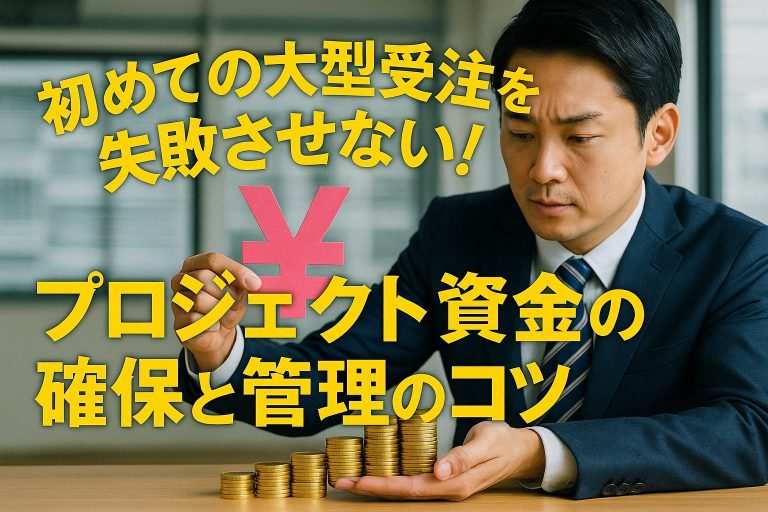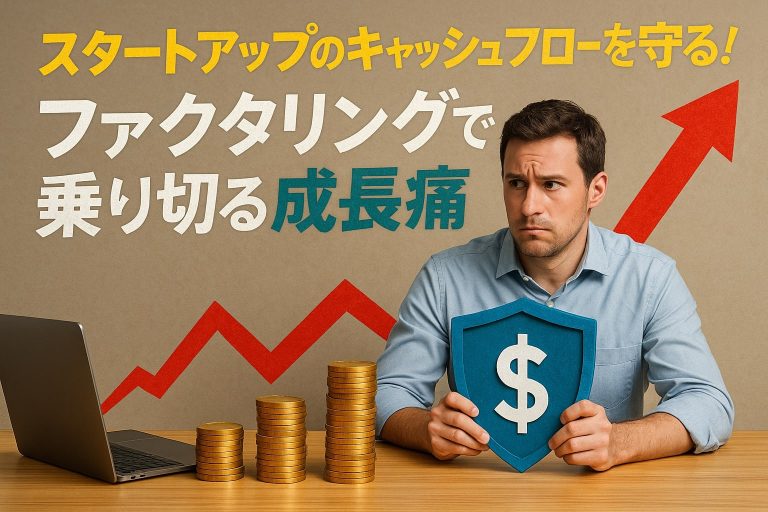中小企業、特にBtoBスタートアップが直面する最大の課題のひとつが「支払いサイト」の長さです。
大企業との取引が始まったとしても、請求書の支払いまで90日、120日と待たされる状況は珍しくありません。
そんな時、銀行融資は審査が厳しく、VCからの資金調達にはエクイティの希薄化という代償が伴います。
実は、この「売掛金と入金の狭間」を乗り切るために、多くの経営者が密かに頼っている「第三の手段」があります。
それが今回ご紹介する「ファクタリング」です。
みずほ銀行での法人営業から独立後、数多くのスタートアップ資金調達に関わってきた私が、サバイバルの現場で培った経験をもとに解説します。
資金繰りの綱渡りを強いられる経営者の方々に、ぜひ知っておいてほしい選択肢です。
支払いサイトの「壁」
取引先は大企業、でも資金は足りない
起業して3年目のAさんは、ようやく大手メーカーとの取引が決まり、歓喜に包まれました。
しかし、その喜びも束の間、「お支払いは検収後90日後」という条件を突きつけられたのです。
社員の給料や外注費は毎月発生するのに、売上の入金は3ヶ月先。
経営計画上は黒字なのに、目の前の資金が底をつきそうな状況です。
これが多くのBtoBスタートアップが直面する「支払いサイトの壁」です。
与信・請求・入金までのタイムラグ
支払いサイトの問題は単に「入金が遅い」だけではありません。
実際には以下のような複数のタイムラグが重なり合っています。
- 与信審査期間(取引開始前)
- 納品・検収までの期間
- 請求書発行から支払期日までの期間
- 支払処理の事務手続き期間
特に大企業との取引では、この全工程で平均4〜6ヶ月のタイムラグが生じることも珍しくありません。
この間、スタートアップは全てのコストを先行投資として負担し続けなければならないのです。
起業初期に陥りがちな「黒字倒産」のリスク
驚くことに、倒産する企業の約3割は「黒字倒産」だと言われています。
会計上の利益が出ていても、実際の現金が不足すれば、企業は立ち行かなくなるのです。
私がみずほ銀行時代に目の当たりにした光景は、「次の大型案件が決まったから大丈夫」と笑顔で語っていた社長が、その入金を待たずして倒産した悲劇でした。
損益計算書(PL)は健全でも、キャッシュフロー計算書(CF)が悲鳴を上げている状態—これが「黒字倒産」の本質です。
ファクタリングとは何か?
基本の仕組みと2つの主要タイプ
ファクタリングとは、簡単に言えば「未回収の売掛金を売却して早期に資金化する方法」です。
具体的には以下の流れになります。
1. 売掛債権の譲渡
- スタートアップ企業が持つ売掛金(請求書)をファクタリング会社に売却する
- 売掛金の額面から手数料を差し引いた金額を受け取る
- 売掛金の支払期日を待たずに即日〜数日で資金化できる
ファクタリングには主に2つのタイプがあります。
【2つの主要タイプ】
①2社間ファクタリング:
利用企業とファクタリング会社の間だけで完結。売掛先企業には通知されない。②3社間ファクタリング:
売掛先企業にも通知し、支払いの同意を得る方式。手数料は比較的低め。
特に創業期のスタートアップにとって、取引先に知られたくない場合は2社間ファクタリングが選ばれることが多いです。
銀行融資やVC資金との違い
銀行融資、VC資金調達、ファクタリングの主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 銀行融資 | VC資金 | ファクタリング |
|---|---|---|---|
| 調達の速さ | 1〜3ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 最短即日 |
| 審査基準 | 財務状況・担保 | 事業性・成長性 | 売掛先の信用力 |
| 返済義務 | あり | なし(株式) | なし(債権売却) |
| 経営への関与 | 少ない | 大きい | なし |
| コスト | 年利1〜15% | 株式希薄化 | 手数料5〜30% |
ファクタリングの最大の特徴は「借入ではない」ということです。
銀行融資のように返済義務が生じるわけではなく、自社の売掛債権を売却するという取引形態をとります。
そのため、貸借対照表上も「負債」として計上されず、財務体質を悪化させない点が大きなメリットです。
よくある誤解とその真実
ファクタリングに対しては、いくつかの誤解が存在します。
「ファクタリングは高利の借金だ」という声をよく耳にしますが、これは正確ではありません。
ファクタリングは借入ではなく債権売買取引であり、法的にも金融庁が定める貸金業には該当しないのです。
手数料が高いという批判もありますが、これは「融資」と比較した場合の話であって、「売掛金を早期に現金化する」というサービスの対価と考えるべきでしょう。
また「経営状態が悪い企業が使うもの」というイメージもありますが、実際には成長中の優良企業こそ、成長資金を素早く確保するためにファクタリングを活用しています。
事実、私のクライアントには東証マザーズに上場した企業も含まれていますが、成長フェーズではファクタリングを戦略的に活用していました。
スタートアップがファクタリングを使うとき
どんな場面で役立つか?—実例紹介
ファクタリングが特に効果を発揮するのは、以下のようなシーンです。
- 大企業との取引開始時
あるITスタートアップは、大手自動車メーカーとの初取引で800万円の案件を獲得しました。
しかし支払いサイトは120日。
開発チームの人件費をまかなうため、ファクタリングで720万円(手数料率10%)を調達し、プロジェクトを無事完遂しました。 - 急な大型案件対応時
セキュリティシステム開発のBさんの会社は、突然の大型案件を受注。
必要な機材や外注費用として2,000万円が急遽必要になりました。
既存の売掛金1,500万円をファクタリングで資金化し、残りは自己資金で対応。
結果的に3,500万円の利益を生み出す案件を逃さずに済みました。 - 季節変動の乗り切り
EC支援を行うCさんの会社は、毎年11〜12月の繁忙期に人材を大量採用する必要がありました。
しかし売上入金は翌年2〜3月に集中するため、ファクタリングで一時的な資金ギャップを埋め、成長機会を最大化しています。
メリットだけでなく、デメリットも理解する
ファクタリングの主なメリットとデメリットを冷静に見ていきましょう。
【メリット】
- 最短即日での資金調達が可能
- 創業間もない企業でも利用できる
- 決算書や担保が不要(売掛先の信用で判断)
- 負債にならず財務体質を悪化させない
- 資金調達の多様化につながる
【デメリット】
- 手数料率が比較的高い(5〜30%程度)
- 利用頻度が高いと収益性が低下する
- 2社間方式では取引先との関係に影響する可能性
- 業界内に悪質業者も存在する
私が常に強調するのは、「ファクタリングは一時的な資金ギャップを埋めるための手段であり、恒常的な資金不足の解決策ではない」ということです。
持続的に利用するビジネスモデルでは、結果的に利益率を大きく圧迫してしまうでしょう。
ファクタリング会社の選び方と注意点
良質なファクタリング会社を選ぶポイントは以下の通りです。
1. 手数料の透明性
- 最初から明確な手数料率を提示しているか
- 契約書に隠れた手数料がないか
2. 実績と信頼性
- 設立年数や取引実績
- 金融庁への登録有無(登録貸金業者か※ファクタリングのみなら不要の場合も)
- 公式サイトの情報の充実度
3. 対応の丁寧さ
- 質問への回答が明確か
- 無理な営業をしてこないか
- 事業内容への理解を示しているか
4. 契約内容の明確さ
- 遅延時のペナルティ条項
- 二重譲渡防止措置の有無
- 秘密保持条項の確認
特に注意すべきは、「担保」や「保証」を要求してくる業者です。
本来のファクタリングは債権売買であり、担保や保証は不要なはずです。
このような要求をしてくる業者は、実質的には高金利貸付を行っている可能性が高いため避けるべきでしょう。
資金繰りのリアル:現場の声
「助かった」だけじゃない——現場の葛藤
私がこれまでサポートしてきた経営者たちは、ファクタリングの利用に関して複雑な心境を抱えていました。
「正直、最初はファクタリングを使うことに抵抗がありました。何となく後ろめたさを感じたんです。でも、あのとき使わなければ、従業員20人の給料が払えなかった。結果的に会社を守るための決断だったと思います」
これは、医療機器開発ベンチャーの社長の言葉です。
多くの経営者がファクタリングの利用を公言したがらない理由は、「経営が苦しい」と思われたくないという心理が働くからでしょう。
しかし、実際にはキャッシュフローの最適化という財務戦略の一環として捉えるべきです。
ビジネスの成長スピードと資金調達のタイミングのミスマッチは、多くの企業が直面する普遍的な課題なのです。
ファクタリングに頼るしかなかった経営者の決断
製造業のスタートアップを率いるDさんは、創業2年目に大手自動車部品メーカーからの大型受注を獲得しました。
喜びもつかの間、材料費や人件費の支払いが先行し、銀行融資も間に合わない状況に。
「倒産か、ファクタリングか」—この二択を前に、Dさんは苦渋の決断を下しました。
「売掛金1,000万円に対して250万円の手数料を支払いました。率直に言って痛かった。でも、この判断のおかげで会社は存続し、今では年商3億円まで成長しました。あの時の判断は間違っていなかったと思います」
このケースが示すのは、「短期的なコスト」と「長期的な機会損失」のバランスです。
ファクタリングの手数料は確かに高額ですが、大きなビジネスチャンスを逃すコストや倒産のリスクと比較すれば、合理的な選択肢になり得るのです。
会計処理・税務対応の実際
ファクタリングを利用する際、会計処理や税務上の取り扱いも重要なポイントです。
会計処理の基本パターン
【ファクタリング利用時の仕訳例】
(売掛金1,000万円、手数料100万円の場合)
1. 売掛金の売却
借方:現金預金 9,000,000円
借方:支払手数料 1,000,000円
貸方:売掛金 10,000,000円
2. 売掛先からファクタリング会社への支払い
(仕訳不要 ※既に売掛金がオフバランス化されているため)税務上は、支払手数料は損金(経費)として計上できるため、課税所得の減少につながります。
ただし、多額のファクタリング手数料が発生している場合、税務調査で「資金繰りの実態」について質問されるケースもあるため、理由を説明できるようにしておくことが重要です。
また、消費税の取り扱いについては、売掛金の消費税部分も含めてファクタリング会社に譲渡することになりますが、支払手数料には別途消費税がかかる点にも注意が必要です。
ファクタリングは”最終手段”か?
「知らなかった」では済まされない資金調達リテラシー
「ファクタリングは最終手段」—この言葉をよく耳にします。
しかし、私はあえて異論を唱えたい。
最終手段ではなく、「状況に応じた選択肢のひとつ」と捉えるべきなのです。
銀行融資、エンジェル投資、VC、クラウドファンディング、補助金、ファクタリング—これらはすべて状況に応じた「選択肢」にすぎません。
経営者として重要なのは、それぞれの特性と自社の状況を理解した上で、最適な手段を選ぶ「資金調達リテラシー」です。
ファクタリングについて知らなかったために、ビジネスチャンスを逃したり、最悪の場合は倒産してしまったスタートアップを私は数多く見てきました。
「知らなかった」では済まされない—それが経営者としての現実です。
竹内流・資金ショートを防ぐ思考法
私が多くのクライアントに伝えている「資金ショート防止の思考法」を共有します。
1. 90日先までのキャッシュフロー予測を常に持つ
- 週次での資金繰り表の更新
- 最悪シナリオを含めた複数パターンの予測
- 入金遅延リスクの織り込み
2. 資金調達手段のポートフォリオを構築する
- 複数の銀行との関係構築
- ファクタリングを含む緊急時の調達手段確保
- 公的支援制度の把握と申請準備
3. 「デッドライン」を常に意識する
- 資金がショートする可能性がある時期の3ヶ月前を「デッドライン」と設定
- デッドラインを過ぎたら、あらゆる手段を検討する覚悟を持つ
- 感情ではなく、数字で判断する習慣を身につける
資金繰りは「綱渡り」ではなく「航海」であるべきです。
嵐(資金ショート)が来る前に、複数の避難港(資金調達手段)を知っておくことが、経営者の責任なのです。
その時、経営者として何を選ぶか?
最終的には、あなた自身が経営者として何を優先するかの問題です。
私がみずほ銀行時代に見てきた経営者の姿は、様々でした。
「高額な手数料を払っても会社を存続させる」という選択をする人もいれば、「原則を曲げずに潔く撤退する」という判断をする人もいました。
どちらが正解かは、その人の価値観次第です。
しかし、少なくとも「選択肢を知らなかった」という理由で、大切な会社や従業員の未来を失うことだけは避けてほしい。
それが私がこの記事を書いた最大の理由です。
ファクタリングが「最後の手段」であろうとなかろうと、それは経営者としてのあなたが持つべき「知恵袋」の一部です。
その知恵を、いつ、どのように使うか—それを決めるのはあなた自身なのです。
まとめ
ファクタリングは「知恵袋」であって「魔法」ではありません。
適切に使えば資金繰りの強力な味方になりますが、過度に依存すればビジネスの収益性を圧迫する諸刃の剣でもあります。
重要なのは、「緊急時の選択肢を増やしておくこと」と「冷静に判断できる財務感覚を磨くこと」です。
経営は常に選択の連続です。
その選択肢を少しでも多く持ち、適切な判断ができるよう、日頃から資金調達の知識をアップデートし続けてください。
最後に、私の恩師が教えてくれた言葉を共有します。
「資金繰りは経営者の命綱だ。それを守るためなら、プライドを捨てることも時には必要だ」
地に足のついた資金戦略こそが、スタートアップサバイバルの鍵なのです。